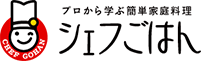ピックアップシェフ

料理人になるならイタリア料理。中学生でピッツァを生地から作っていた。
料理人になろうと決めた、母のありがたい言葉。
僕は埼玉県川越市の出身です。川越ば「小江戸(こえど)」とも呼ばれ、最近では古い町並みが残る歴足ある街として、海外からも観光客がやってくるほどの街になりましたが、僕が住んでいた当時はごく普通の地方都市でした。父はサラリーマン、母は専業主婦だったので全く飲食店とは縁のない家庭で育ったんです。ましてや父親は外食よりも、家で食べる食事がいちばん、というタイプだったので、レストランに行けるのも年に1、2回ぐらい。近所の蕎麦屋でもファミレスでも、滅多に行けないので、連れて行ってもらったときはすごく嬉しかったですね。
父は器用な人で、モノが壊れてもすぐに買わないで修理する、作るという人。そんな父を手伝って、小さいときから日曜大工をやっていました。一緒に壊れた家具を直したり、棚を作って吊ったりとか、楽しく手伝っていました。モノを作るのがすごく好きでしたし、父に似たのか、僕も手先が器用な子供でした。
我が家の食卓には、父の好物中心の献立が毎日上がっていました。子供向けのものはあまりなかったんですよね。でも、小学校に入って給食が始まると、子供好みのおいしいおかずが食べられる。そのメニューを母に再現してほしいとせがみ、僕も台所に入って一緒に作っていました。キュウリの中華風のあえ物とか、ごく普通の料理です。でも母の手伝いで味わった料理の楽しさが、料理に目覚めるきっかけだったように思います。家にあったレシピ本を見て、食べたいものを作ったり、中学生になってからはピッツァを生地から作って焼いて、友人に食べさせたりしたこともあります。いま思えば、発酵が中途半端でイースト菌くさくて全くおいしくなかったんですが(笑)、食べたい一心でチャレンジしていました。でも「将来、料理人になる」とは全く考えていなかったんです。高校を出たら、とにかく親元を離れて自立したい、働きたいと思っていました。就職活動を始めた矢先、母がふと「あなたはもう料理に未練はないの?」と言うんです。

ボンゴレの味に感動して決めた最初の修業先『アントニオ』。
正直、ハッとしました。頭のどこかにあった料理をやりたいという気持ちが、母の言葉で現実的なものになりました。だけど、もう親に甘えたくない、自立したいんだ、という気持ちも強く、心が揺れていました。すると「このまま就職するのはもったいないと思う。とりあえず料理の勉強をしてみたら?」と母に言われました。そう聞いて気持ちがラクになり、専門学校でやってみて、もし合わなかったらやめよう、という結論を出し、池袋の調理師学校に入学しました。学校では、料理実習は面白かったので真面目に出席し、成績も良かったのですが、栄養学などの筆記試験は苦手でしたね(笑)。もうそのころはイタリアンの料理人になりたいと決めていました。フランス料理に比べて、パスタやピッツァを筆頭に僕には身近な料理だったからです。その年はちょうど大ブームだったティラミス人気がだいぶ落ち着き、そろそろパンナコッタに人気が移る時期でしたね。イタリア料理の人気はまだまだ高かったです。
就職先を探す時期が来たとき、ホテルではなく、町場のレストランで働きたいと思っていました。でも学校には求人がなく、自分で探すしかない。その当時、肉体労働系の『ガテン』という求人誌があったんですが、そこで見つけたのが『アントニオ 代官山』でした。当時は全く知らない店でしたが、「創業50年、日本でいちばん古いイタリアンレストラン…」というコピーにピンと来たんです。すぐに電話して面接することになりました。
初めて訪れた『アントニオ 代官山』。その重厚なインテリアと高級な雰囲気に、19歳の僕は圧倒されました。面接が終わった後、せっかくだから料理を食べていきなさいと言われ、ボンゴレとピッツァを出してくださったんですが、そのボンゴレは人生19年で食べた中で最も感動したほどの、とんでもないおいしさでした。そのボンゴレのおかげで「ここで働く」と決心したようなもの。だから給料面など肝心なことは全く聞かずに入社してしまったんです(笑)。

イタリアに行ってもっと知りたい、学びたいという気持ちが募っていった。
バブルは既に弾けたとはいえ、『アントニオ 代官山』にいた2年間は、とにかく忙しかった、という思い出ですね。新人はまず1年間はサービスをやらされるので、店の下働きに駆けずり回り、さらに『ヒルサイドテラス』で行われるウェディングの出張ケータリングの手伝いもあり、毎日、目の回るような忙しさでした。2年目からはキッチンに入れましたが、そんな風に忙しい職場なので、辞める人も多く、どんどん仕事が増えてきて、手打ちパスタやメイン料理の手伝いまで担当することになりました。料理が覚えられるのは良かったですけど、まぁ僕も辛いことがいろいろあって、退社することにしました。いま思えば、もう少し頑張って3年ぐらいいても良かったかなと思うけど・・・。でもその期間にお世話になった先輩たちには、その後もいろんな形でお世話になりましたし、同期入社だった『ICARO miyamoto』のシェフ・宮本義隆くんとは、いまも親友です。だから『アントニオ 代官山』で知り合った方々にその後も助けられたし、ありがたかったですね。
辞めた僕に声をかけてくれたのも、そんな先輩の1人でした。間もなく独立して店を始めるので来てくれないか、と。その先輩はイタリアで修業したのち『アントニオ 代官山』で働いていた方で、すごく仕事ができる憧れの方です。ありがたくお誘いを受け、その店、石神井の『ロニオン』のオープンから働くことになりました。『ロニオン』で働き始めた僕は、シェフの影響もあり、「イタリアで修業してみたい」という気持ちがどんどん高まっていきました。当時24歳だったので、25歳でイタリアに渡り、30歳まで働きたいという希望を持っていました。同期の宮本くんが24歳でイタリアに行ったことも大きな刺激になりましたね。本当に行っていいんだ、行けるんだ、って。シェフには「イタリアに行くことを考えると同時に、帰ってきた後の場所も作っておきなさい」とアドバイスをもらいました。その頃はイタリアに行きたい、でもお金も貯めたい、実績も残したい・・・と様々な思いに囚われる日々を送っていました。 (後半に続く)

ピエモンテ州で生まれた料理 『バーニャカウダ』
日本でもすっかり浸透した『バーニャカウダ』は、僕が5年間修業したピエモンテ州の郷土料理で、今や世界中に広まったものです。店で食べるというより家庭料理ですね。うちの店でも開店当初は出していましたが、いまはありません。イタリアに渡る前に働いていた東京のレストランで作り方を教わりましたが、すごく簡単に作ってしまっていて、クオリティの点ではいまひとつでした。しかしピエモンテに行ってびっくり。というのも、材料は「あそこのアンチョビじゃないとダメ」とか「オリーブオイルはこれがベスト」とか、家庭ごとにすごいこだわりあるんですよ。それが面白かったですね。そういう地元ならではの“こだわり”があるから、郷土料理には魅力があるんですよね。
『バーニャカウダ』のおいしさの決め手は、ソースをしっかり乳化させること。そのためにはにんにくにじっくり火を通して柔らかくし、独特の刺激臭をとることです。固めの野菜はさっと茹でてから食べたほうがおいしいし、色目もきれいだと思います。どんな野菜でもおいしくいただけるソースです。余ったら落としラップをして冷蔵後に保存すれば、2週間ぐらいは持ちます。
バーニャカウダ

コツ・ポイント
にんにくの茹で時間は1~1時間半かかります。 指でつぶれるほど柔らかくなったらOK。独特の臭みも消えます。時間が短いとにおいが抜けないので注意。 オリーブオイルを混ぜるときは、ミキサーやブレンダーなどを使って、しっかり乳化させてください。