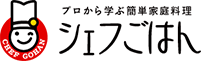ピックアップシェフ

フランス各地で学んだ地方の味と都会のエスプリを日本人の感性で融合したい。
料理上手な母が作れないフランス料理をやってみたかった。
私は大阪の摂津市で生まれ、昔もいまも変わらず仲の良い両親と弟の4人家族で育ちました。父は母の手料理を家で食べるのが何よりも幸せ、という人なので、家族で外食に行った記憶がほとんどないんです。母も働いていたので「お米を2合研いでおいてくれる?」と私に“指令”が入るんです。帰宅した母が調理をする隣で、野菜を洗ったり皮をむいたり、自然に台所で手伝っていました。そのうちだし巻き卵などの料理も作るようになり、母も「卵焼きは健が作ったほうがおいしい」とか、父に「健がよそったごはんはうまいな」など、今思い起こせば、うまくノセられていたという気もしますが(笑)、この自分が手伝った、おいしいおかずが並ぶ食卓は、私の食の原体験になっていると感じています。
高校卒業後に調理師専門学校に進んだのも自然なことでしたし、両親もすぐに納得してくれました。そのときから目指したのはフランス料理のシェフ。というのは、母が作れない料理をやりたい、それがフランス料理だったからです。就職先は多くの同級生が希望するホテルではなく、町中のレストランで働きたいと思っていました。レストランのガイド本で探したレストランを食べ歩きし、ここで働きたいと思ったのが京都の『ラ・ヌーヴェル・フォンテーヌ』(現在は閉店)でした。
オーナーシェフの多々内氏はフランスで長く修業された方で、風貌も生き方も作る料理もフランス人そのもののような人でした。当時、多々内シェフはフレンチブルーの「ルノー・アルピーヌ」という車に乗っておられ、その姿がめちゃくちゃカッコよくて、憧れていましたねぇ。そういうシェフのもとで働いていたので、自分も将来はフランスに渡って修業するのは当たり前だと思っていました。

フランス・バスクの素朴で温かい人々と豊かな山の食材に魅せられた。
フランスに渡ったのは24歳のとき。2001年の9・11テロがあった1か月後だったので、空港はどこも警戒が厳しく、初めて行く外国で緊張した記憶は忘れられません。そして最初に住んだ町がリヨンでした。当初は働くツテもあてもなかったので、まずはリヨンの語学学校に入学したんです。まもなく地元のビストロに運よく雇われ、朝から働いて、午後は学校に行き、夕方からまた仕事、という毎日が始まりました。料理修業というよりもアルバイトでしたけど、異国で生きていくスタートとしては、いい経験でした。
その後はアルザス地方で短期間働いた後、雇ってくれるよう手紙を送ったバスク地方にあるレストランへ移りました。
バスクでの生活は約1年間ですか、その生活は本当に素晴らしいものでした。近年、新しい食の潮流の発信地として知られるバスク地方ですが、海に面したスペイン・バスクと違って、フランス・バスクは山あいに小さな集落が寄り集まった地域。住み込みで働いていたレストランのある村はピレネー山脈の中にあり、帰るたびに耳の奥がキーンと痛くなるほどの高地でした。何がいいって、バスクは人が素晴らしいんですよ。集落ごとに毎週、小規模なお祭りがあり、どこに行っても日本人というと歓迎され、飲み代は一度も払ったことがなかったですね。気持ちの温かい人に恵まれて、毎日楽しく働いていました。料理に関しても新しい経験がいろいろでき、感動したことがたくさんありました。例えばフォアグラの準備と言えば、冷蔵庫の中にぎっしり詰まった丸ごとの鴨を一匹ずつさばき、まずフォアグラを取り出して、脚はコンフィにして、脂身はリエットにして・・・という作業です。最後に残った骨も焼いて、まかないでかじりついて食べるんですが、それがまたすごくおいしいんですよ。

フランス料理の固定観念に囚われない自由な発想のシェフとの出会い。
しばらく山で働いたので、海辺の街でも働きたくなり、ブルターニュやニースなどシーフードがメインのレストランや、ホテルの厨房でも経験を積みました。フランス~スイスで合計8年間働きましたけど、どこの街でもたくさんのことを学び、地方色豊かな食文化、その地域に根付いた食材の素晴らしさには、何度も感動させられました。フランスに行く前、父に「フランスは農業大国だから、いろんな地方を回るといい」とアドバイスされたのですが、その言葉を確認することができましたし、私自身、いろんな場所を回れば、違うものが見られるだろう、という好奇心が人一倍強かったのも良かったんでしょうね。そのころは日本に帰りたくない、と本気で思っていましたから。
最後にパリに移り、元『タイユヴァン』のシェフ、ミシェル・デル・ブルゴ氏が始めた『オランジュリー』でオープニング・スタッフとして働いた後、それまで自分が持っていたフランス料理の固定観念を打ち砕くほどの存在、『シャトーブリアン』のシェフ、イナキ・エズピタルト氏に出会いました。たまたま『シャトーブリアン』で働きたいという日本人料理人の通訳として『シャトーブリアン』を訪ねると、イナキシェフに「きみはいま何をしているの?」と聞かれ、「フリーです」と答えると、「ここで働かないか」と誘われて(笑)。
イナキシェフは元庭師いう異色のキャリアの持ち主で、料理はほぼ独学の人。良い意味で合理的で、フランス料理の形式にとらわれない料理人でした。ある日私が「ローリエはどこ?」と聞くと、「無いけど、必要なら買ってくるよ」と言うんです。びっくりですよ。厨房にローリエが無い店なんて。決まりごとのように使っている塩コショウやハーブなども、本当に必要なのかどうか“自分の味覚”で判断して決めればいい、不要なら使う必要はない、というのが彼の考え方。大事なのは自分の舌とイマジネーションというのかな。店には昼夜毎日満席で100人ものお客さんが来ます。厨房はたった3~4人で目の回る忙しさでしたけど、イナキシェフの独創的な料理を見るのは本当に楽しかった。そして私自身もここで過ごすうちに、自分らしい料理を表現したいという気持ちが日に日に高まっていきました。 (後編に続く)

フランス人が大好きな清涼感いっぱいの夏の前菜『トマトとミントのタブレ』。
今回お教えする料理はクスクスを使った『トマトとミントのタブレ』。フランス人が大好きな料理です。
24歳のとき初めてフランスのリヨンについた日、何か食べるものを買いに行こうと町のスーパーに行き、デリコーナーで初めて買って食べたのが「タブレ」でした。つまりフランスではじめて食べた思い出の料理でもあるんです。しかしそのパック入りのタブレは味も薄くてパサパサで、おいしくなかったので、塩コショウやレモン汁を足して食べましたけどね(笑)。
ニースにある有名なホテル『ホテル ネグレスコ』で働いているときに出会ったのが、このトマト味のタブレです。ホテルにはレストラン、カフェ、バンケットと3つの厨房があったんですが、カフェの女性シェフがまかない用に作っていたのがこれ。もらって食べたらすごくおいしかったんですよ。それ以来、クスクスはトマトジュースを入れて柔らかく戻すのが私の定番になりました。
基本の戻し方はクスクスと水が同量でいいと思います。昔ニースで食べたものよりも、レシピを進化させてさらにおいしくなっていると思います。野菜はみずみずしい夏の野菜ならなんでも合いますし、フレッシュなミントをたっぷり入れるのもおすすめです。おいしい食べ方は冷蔵庫に入れずに、できたてをすぐに食べること。そして食べながら自分好みの味つけでいただく料理なので、塩コショウやレモン汁を添えて、各自自由に味を足して召し上がってください。
トマトとミントのタブレ

コツ・ポイント
クスクスを戻す時にトマトジュースを加えてコクを出し、ミントとレモン汁でさっぱりとさせます。冷蔵庫でキンキンに冷やすよりもさっと合わせて出来立てを食べる方が、野菜やセモリナ粉の風味が出て美味しいです。