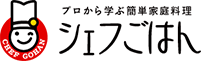名店のまかないレシピ

25年前、東京・西麻布に店をオープンして以来、多くの人々の舌を魅了し続けるリストランテ「アクアパッツァ」。その店名にもなった一皿は、素材の味を活かすイタリア郷土料理の豊かさを日本中に伝えてきました。オーナーの日高良実シェフにとって、まかないとは自身の料理人生を決める転機にもなった大きな存在なのだとか。取材が行われたのはアクアパッツァの「25歳の誕生日」であるその日。まかないの思い出と共に、愛される店づくりのために日高シェフが大切にする価値について語っていただきました。

25年の歴史と共にある、まかないの思い出
今日は昔の修業時代に自分でよく作っていたまかないをイメージしながら、2品の料理を作ってみました。牛すじのどんぶりに焼きうどん。炭水化物のかけ合わせで不思議に感じるかもしれないですが、私の出身の関西ではよくある組み合わせ。当時、中華料理のレパートリーは酢豚か八宝菜くらいしかなくてね。でも、簡単ですぐにできるから、まかないの定番でしたよ。
西麻布に初めて自分の店を構えた時から、まかないにはいろいろな思い出がありますね。オープン当初はスタッフも5~6人くらいしかいなくて、ランチ営業が早く終わった日は、中庭に出てみんなでおむすびを食べたりね。いただきもののワインもちょっと楽しんで、ディナー営業まで昼寝して。チップが貯まったら皆でいい肉を買ってきて、焼いたりもしたことが懐かしいですね。桜の季節なんて最高な気分でした。
あれから25年経って、当時に比べると大所帯になりましたが、まかないの基本は変わらず、スタッフの心身を形成するための「体にいいもの」を提供することが一番。1日2回、ランチ営業前の11時には余った材料でパスタソースを作って厨房で“立ち食いパスタ”をかき込んで、15時くらいにしっかりしたまかないを出しています。私も店にいる日は一緒に食べています。
担当は新人から中堅くらいまでのスタッフが交代で、上階の姉妹店「アクアヴィーノ」のスタッフと合同で当番制にしています。献立は特に指定せずに、作りたいものを自由に。お客様からのご注文ではなく、「自分で何でも決められる料理」というのはまかないくらいしかないですから、貴重な修業であり自己アピールの機会になりますよ。今日みたいなどんぶりは作るのは簡単だけれど、そればかりだと創造性が育まれないから「たまにはイタリアンも作りなさい」とは言いますね(笑)。
それに、“感想”を言い合うことも大事。うまいもまずいも、率直に言い合うことでお互いに磨き合えるんですから。先輩や師匠からリアクションを受け取って、時に恥をかき、悔しい思いもしながら、おいしいものを作るためにまた努力する。そうやって料理人の基本の精神が育っていくのではないかと思っています。

イタリア修業の原点は、まかないカルボナーラ
まかないにはレストランのチームを盛り上げる力もあるのだと、今あらためて感じます。皆を満足させたいからと朝7時台から厨房に入って仕込みをする、麺打ちからラーメン作りを始める、ほかほかの新米でおにぎりを握る・・・そんなまかないのシーンが店に生まれるだけで、自然とチームは盛り上がるんです。長く愛され続ける店づくりには、そんなささやかなまかないの光景が大切なのかもしれませんね。
振り返れば私自身の料理人生にとっても、まかないは大きな転機のきっかけになりました。神戸ポートピアホテル「アラン シャペル」で働く前、4カ月間働いたイタリアンレストランのまかないで食べた「カルボナーラ」。カルボナーラというパスタそのものを食べることさえ初めてでしたが、あまりにもおいしくて後半の2カ月間は毎日カルボナーラを食べていたくらい。今思えば茹で上げパスタを温めた、「アルデンテ」も何もないパスタですよ。でも、その時の「おいしい」という感動がイタリア修業を決断する原点になったんです。
まかないは料理人の人生を大きく左右する。私の経験から、そう強く思います。